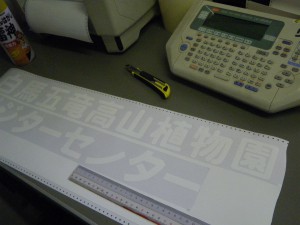いよいよ開園が明日に迫ってきました!
現在咲いている花の情報をお届けします。
園内のコマクサが咲き始めました!
今年は雪が多かったのですが、ロックガーデンの山頂部分は風が強く、積もる雪が薄い場所なので雪解けも早かったものです。
周辺のウルップソウなども咲き始めています。
他にはクロユリ、ハクサンイチゲ、シラネアオイ、ツバメオモト、ノウゴウイチゴなど色々と咲いてきています。オオバキスミレの群生が遠目にも黄色に分かるくらいです。
アルプス平自然遊歩道ではまだ雪が残っている場所もあり、そのためにミズバショウやカタクリが見ごろの場所もまだあります。6月には珍しい雪の感触、通行の際はご注意ください。
明日16日は、いよいよ白馬五竜高山植物園の新規開園です!
皆様のお越しを心よりお待ちしております。